社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~㊻
2025/04/17
Q.オーナー(同族特殊関係者)と同族法人との間の金銭消費貸借契約に係るエビデンスについて教えてください。
A.実務ではそもそも作成をしていないケースが多いのですが、相続税申告や残余財産の分配、DES等々、その実在性について検討しなければならない事態に非常に多く遭遇します。このため下記のエビデンスについて日頃の実務から作成する必要があります。
【解 説】
(1)金銭消費貸借契約 親→子
★1
親子間なので利率の設定まで神経質になる必要はありません(相基通9-10)。元本が大きいもののみ配慮すべきです。
元本:1年後1年分後払い、返済は必須(贈与認定回避)
利息:1年後1年分後払いでも問題ありません。
非常に元本が大きく仮に利率を考慮するなら適正な利率の決定として、
・平均調達金利
・無借金の場合、短期プライムレート以下の金額
になります。法人間と同様の設定でも問題ありません。
上掲契約書の他に通帳間を通した元本の返済が必要です。現金授受では疎明力が一切ありません。借主が未成年者など幼児の場合、法定代理人親署名押印が必要です。この場合、印鑑は別にします。計3種の印鑑が必要になります。
贈与契約の事例ですが、「贈与契約に顕名なしも、代理行為は有効(週刊T& Amaster2022年10月3号・№948)審判所、贈与手続は請求人に包括委任と判断し原処分を全部取消し」についても併せてご参照ください。
(2)金銭消費貸借契約 社長→法人(法人→社長)
★1
上記と真逆であるオーナー借入金については、
・議事録は「できれば」あったほうがよいです。
・金銭消費貸借契約書作成は必要です。
・元本返済のみならず利息の計上も必須です。
★2
利率の設定まで神経質になる必要はありません(パチンコ平和事件)。
元本:1年後1年分後払い(返済は必須)についてもあまり配慮する必要はありません。
★3
利息:1年後1年分後払いでも問題ありません。
利率を考慮するなら適正な利率の決定として、
・平均調達金利
・無借金の場合、短期プライムレート以下の金額
になります。法人間と同様の設定でも問題ありません。
Q.オーナー貸付金(法人にとってはオーナー借入金)について原始証拠がない場合、現時点での証拠保全の方法を教えてください。
A.シリーズ<法人編>でも解説していますが、法人でのオーナー借入金の実在性を担保するため、別途契約書を残すことがあります。いつの時点での残高で債務承認するのかが実務上問題になります。弁護士等によって見解がかなり異なりますが、租税実務の観点からすると、
・保守的に残高を設定したい場合、最大値の残高を使う
・時効を主張するのであれば、時効以降で最大値の残高を使う
後者ですが、本来の当初金銭消費貸借契約時に当事者間で金銭消費貸借の意思の合致は通常していないはずです。ということは時効の起算点が存在しない、という点について事実認定に着地する可能性があります。
法人でのオーナー借入金の実在性を担保するため、別途契約書を残すことがあります。いつの時点での残高で債務承認するのかが実務上問題になります。
弁護士等によって見解がかなり異なりますが、租税実務の観点からすると、
・保守的に残高を設定したい場合、最大値の残高を使う
・時効を主張するのであれば、時効以降で最大値の残高を使う
にせざるを得ません。そして保守的なほうを採用すべきです。
後者ですが、本来の当初金銭消費貸借契約時に当事者間で金銭消費貸借の意思の合致は通常していないはずです。ということは時効の起算点が存在しないとも考えられます。これは事実認定に着地します。
オーナー貸付金(会社では役員借入金)については、契約書の作成は必須です。これは、そもそもが金銭消費貸借であったか、贈与にあたるのか否かの判断における出発点になるからです。金銭消費貸借の契約が仮にない、という場合、
・通帳間での実際の資金移動(ただし、定期的に返済している事実が確認できていることが必須、返済の事実が長期にわたりない場合、贈与認定)
・帳簿記入(勘定科目内訳書作成も含めて)
という間接証拠の積み重ねが必要となります。オーナー法人では帳簿記入はほとんど疎明としては意味がないため(帳簿の記入に恣意性を介入できるから)、通帳間の移動のほうが疎明力は強いです。しかし、いずれにせよ原始契約書がない場合、金銭消費貸借か贈与かに係る事実認定は必ずなされます。
なお、原始契約書がない場合、時効も原則として成立しません。これも事実認定に着地しますが、例えば契約書がない状態で、上記「・」については整理完備されていたとしても、いわゆる時効の起算点が明確にはなりません(通帳間の移動年月日で主張し得るかどうかは事実認定の問題です。)。
仮に時効論点の主張をしたいのなら、かなり保守的な手法ですが、債務承認契約書を作成することで当事者間の意思の合致を証明し、起算点を明確にすることができます。より詳細を研究したい方は最判昭和56年6月30日判タ447号76頁をご参照ください。





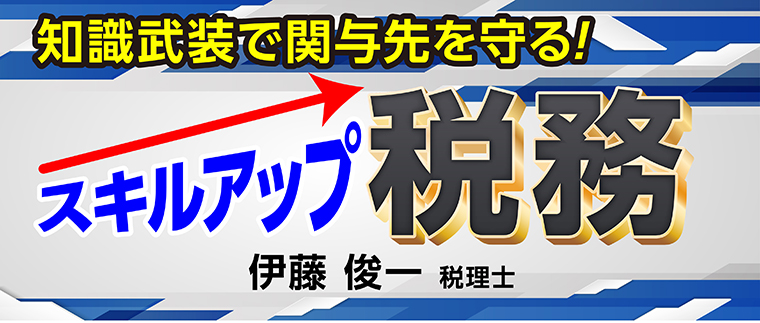




 無料登録はこちら
無料登録はこちら